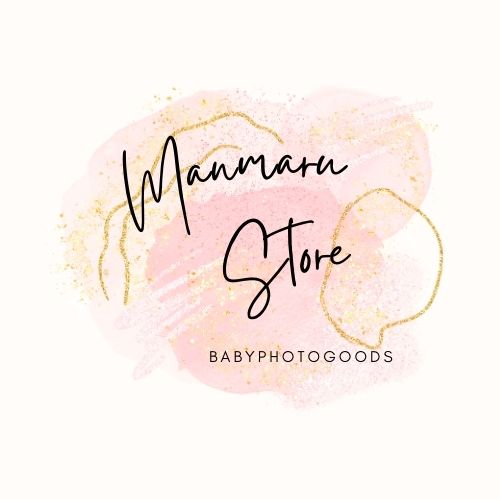夜間授乳が辛いママ!少しでも負担を減らして乗り越えよう

赤ちゃんが産まれて喜びに溢れるのも束の間、産まれたその日から待ち受けている夜間授乳。夜中に赤ちゃんの泣き声で起こされるのは、体力的にも精神的にも苦痛ですよね。いつまで続くか分からない、長い道のりにも思えてしまいます。
・夜間授乳はどうして必要なの?
・どうすれば夜間授乳の負担が減らせるの?
今回はこのようなことについてお伝えします。
赤ちゃんの睡眠リズムはどう変化する?

赤ちゃんの睡眠リズムは成長とともに変化します。個人差は大きいですが、一般的な睡眠リズムは以下の通りです。
生後0〜3か月
新生児は1日の大半を寝て過ごします。1日24時間のうち、14〜18時間寝るのが一般的です。一気にまとめて寝ることはまだできないので、2〜3時間ほどの短いサイクルで目覚めます。新生児はまだ昼と夜の区別ができないため、昼夜問わず同じ睡眠パターンが続きます。
生後3〜6か月
この時期になると、少しずつまとまって寝られるようになり、睡眠の間隔が長くなります。1日のうち12〜16時間ほどを寝て過ごします。夜も5〜6時間ほど連続して寝ることができるようになります。
生後6〜12か月
この時期の赤ちゃんは1日のうちに10〜12時間寝ます。昼間に2〜3回のお昼寝をし、夜は一晩中眠れるようになるので、夜間授乳が不要になる赤ちゃんも多いです。
夜間授乳が辛い理由

睡眠不足
夜間授乳が辛い一番の原因はやはり睡眠不足でしょう。睡眠不足は、疲労感や集中力を低下させ、不安感などを引き起こします。睡眠不足のママは育児に対する不安がつのりやすく、マタニティーブルーなどにおちいりやすいです。
ストレスの増加
夜間授乳により睡眠不足が続くとストレスが増加します。些細なことでイライラしてしまい、なかなか泣き止まない赤ちゃんをうとましく思ってしまうこともあります。そんな自分がさらに嫌になり、ストレスがさらに増して負のスパイラルに陥ってしまいます。
生活リズムの乱れ
夜間授乳で睡眠不足が続くと、生活リズムが乱れていきます。日中にボーッとしてしまい、食欲が無くなります。生活リズムの乱れは体調にも影響し、病気にもかかりやすくなります。
パートナーとの関係性
夜間授乳で睡眠不足が続くと、日中もあまり頭が働きません。パートナーとの会話が少なくなり、コミュニケーション不足の原因になります。夜間授乳でストレスも溜まっているので、パートナーにあたってしまったり、不安を覚えてしまい、関係性を悪くしてしまいやすくなります。
自分の時間がなくなる
夜間授乳により眠れない日が続くと、日中に眠たくなります。やらなければならない家事や上の子のお世話、日中の赤ちゃんのお世話など、などがはかどらなくなると、時間ばかりが経ってしまします。気づけば1日があっという間に過ぎてしまい、ごはんもゆっくり食べられず、自分の時間が全くないという日も少なくないでしょう。
夜間授乳を少しでも軽くするには?

夜間授乳はママが一人でがんばるものではありません。少しでも負担を減らして楽になりましょう。
パパと交代で夜間のお世話をする
一日おきの交代や、週末だけ夜間のお世話を交代してもらいましょう。一日夜ぐっすり寝られるだけでも、翌日の気分が変わります。翌日のスケジュールを確認して、無理のない範囲で相談してみましょう。
授乳しやすい環境にする
授乳姿勢を変えるだけでも、負担は減らせます。ベッドから起き上がるのが大変であれば、添い乳で授乳するのもひとつです。授乳クッションなどで赤ちゃんの姿勢を変えると、赤ちゃんも飲みやすくなります。ベビーベッドまでが遠く、毎回歩いて赤ちゃんを連れてきているのであれば、すぐ隣で添い寝するのもひとつです。
夜間授乳の回数を減らす
少しずつまとめて寝られるようになったら、夜間授乳を少しずつ減らしてみましょう。赤ちゃんが泣いても母乳を与えず、抱っこやトントンで寝かしつけます。最初はとても大変で泣き続ける日もあるでしょう。しかし、赤ちゃん自身も少しずつ学習して、夜は眠るようになります。
ミルクに頼る
母乳よりもミルクの方が腹持ちがいいため比較的長く寝てくれることが多いです。完全母乳でも夜寝る前だけはミルクに頼っても全く問題ありません。少しでもお母さんの睡眠時間を確保することの方が赤ちゃんにとっても良いことなので、もし悩んでいるようであれば迷わず使いましょう。ただしその場合は胸が張って痛くなってしまうこともあるので搾乳を忘れずに行いましょう。
私はこうして乗り越えた!
息子の場合、とにかく頻回授乳でひどいときは1時間起きに授乳をしている状態でした。夜中も例外ではなく「次は何時間眠れるだろうか・・」という不安が常に付きまとい精神状態的にもギリギリの状態でした。上記の方法ももちろん試してみましたがそれでもうまくいかない・・そんな時に「そうだ、寝なきゃ、寝かしつけなきゃと思うから辛いんだ」と開き直り、真夜中でもYouTubeをテレビで流したりスマホで漫画を読んだりしていました。育児本などを見ると授乳中のスマホやテレビはNGとされていますが、ママと赤ちゃんがストレスなく過ごせるほうが100倍大事だと思います。実際それからはストレスは軽減され、徐々に精神的にも落ち着いてくるようになりました。
まとめ

今回は夜間授乳についてまとめました。夜間授乳そのものも辛いですが、その影響が翌日にも続いたり、ストレスが増えたり、いつまで続ければいいのか分からなかったりと、他への影響も多くあります。夜間授乳はママだけが頑張るものではありません。パパと相談して少しでも負担を減らして、ママの笑顔を増やしてくださいね。
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧
MANMARUSTOREとは?
<おうちフォトを楽しみたいママさん向けのグッズ専門店>
●ニューボーンフォト
●月齢フォト
●100日祝い
●ハーフバースデー
●誕生日 etc…
記念日に使える可愛いアイテムが盛りだくさん!



おうちスタジオを作るお手伝いを致します♡
是非下記リンクからご覧くださいね
୨୧‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥∵‥୨୧